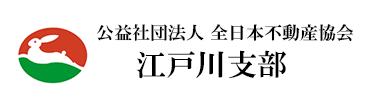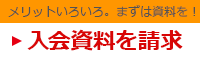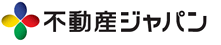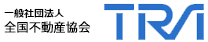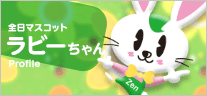経済・不動産レポート
当支部が毎月発行する『経済・不動産レポート』です。
※ レポートのタイトルをクリックするとダウンロードできます
-
2023/07/21「仕事に活かす経済・不動産レポート」(2023年7月号)
6月以降、バブル崩壊後の高値更新が続いていた日経平均ですが、7月に入るとやや失速の兆しを見せ始めています。そもそも、日本株がポジティブに推移するようになったのは、世界的なカリスマ投資家であるウォーレン・バフェット氏が日本の総合商社株の組み入れに動いたことがきっかけとみられています。バフェット氏はさらに日本株を買い増す姿勢を示しており、日本の株式市場全体に対しても強気のコメントを発言しています。
また、①我が国の企業収益が回復に向かっていること、②企業が株主還元に前向きに取り込みつつあること、③中国リスクの高まりによって日本株シフトが起こっていること、といった要因も株高を支えているようです。中国リスクとは、人口減少社会への突入、経済成長率の低下、デフレ経済突入の懸念、公的債務の比較的増大といった問題であり、まさしく我が国が30年前にたどった道を歩もうとしているかのようです。
【2023年7月号のサマリー】
1.住宅着工戸数と中古及び新車自動車販売台数の推移。貸家の増加と中古軽自動車の増加が連携?
2.都道府県別にみた軽自動車の新車販売動向!軽自動車はセカンドカー、郊外需要が強いと推察。
3.中古自動車販売と新車自動車販売の長期推移と注目点!普通自動車と軽自動車の二極化が進展。
4.パーク24の決算にみる駐車場市場の動向と成長ビジネスとは?モビリティ事業が成長のドライバーに。
5.企業の生産活動、消費活動は全体としてはポジティブな傾向が継続しているが、一部に失速・減速感も。
6.ジェンダーギャップ報告書にみる我が国のジェンダーギャップの実態とは?我が国の順位は過去最低を更新。
7.非正規雇用者の長期推移と年齢階層別動向について。不動産業は非正規社員の比率が低いのが特徴。
8.株式市場では日米ともポジティブな展開であり、日経平均はバブル崩壊後、米国は年初来高値を更新。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2023/06/24「仕事に活かす経済・不動産レポート」(2023年6月号)
6月以降、日本の株式市場が非常に強い展開となっています。日経平均株価は33年振りにバブル崩壊後の高値を更新し、一段と先高感が強まっています。強気な見方では、年内にもバブル期の最高値38,915円を更新し、4万円に乗せるのではないかといった声も聞こえてきます。実際問題、株式市場は過熱感があり、このまま一本調子で上げていくこと考えにくいと思われますが、投資家のマインドが大きく好転してきたことは間違いなさそうです。
何故、日本の株式市場が再評価されるようになったかというと、外国人による買いがきっかけとみられています。その要因として、①我が国の企業が経営改革により収益力を改善する期待が高まってきた、②株主還元に前向きな企業が増えてきた、③中国経済の失速によって我が国経済に対する評価が再認識されている、④デフレからの脱却によって潜在成長率が高まるとの見方が出てきた、といった点が挙げけられます。
【2023年6月号のサマリー】
1. 何故、持ち家着工は長期に渡ってマイナスを続けているのか?住宅価格上昇と所得環境の悪化が要因か。
2. コロナ禍における東京都の住民基本台帳に基づく人口移動状況!再び東京一極集中の流れに回帰。
3. コロナ禍における主な業態別小売業の売上高推移!ドラッグストア好調、スーパー堅調、百貨店回復。
4. パート・アルバイトの募集時賃金は過去最高水準に!エッセンシャルワーカーの時給が大きく上昇している。
5. 企業の生産活動、消費活動は全体としてはポジティブな傾向が継続しているが、一部に失速・減速感も。
6. 不動産市場に異変!企業の移転により淡路島など地方圏で不動産バブル発生か?今後の行方は?
7. 観光DI及び項目別内訳、日本人及び外国人の宿泊者数の推移。観光産業は復権を遂げた。
8. 株式市場では日米ともポジティブな展開であり、日経平均はバブル崩壊後の戻り高値を更新している。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2023/05/29「仕事に活かす経済・不動産レポート」(2023年5月号)
全日本不動産協会 東京都本部編集
ゴールデンウィークを終えても、人流が増加し、経済活動も回復基調を強めてきました。全国観光地は観光客が賑わって、都心部の百貨店ではコロナ禍前の売上高水準を回復し、新幹線、飛行機、ホテルも予約が取りにくくなってきました。5月に発表された企業の決算も概ね順調で、過去最高利益を計上する企業が散見されました。
こうしたなかで、企業は「人手不足」「賃金アップ」「インフレ対策」に取り組まなければなりません。特に、人手不足問題に関しては、景気回復とともに一部の業種では深刻な問題となっており、人手不足によって思うように事業に取り組めないといった事態が起こっています。
特に、飲食、旅館・ホテル、建設といった分野では、人手不足を背景に収益機会を逸してしまっているといった状況も聞かれます。こうした業種では、賃金アップによる求職者の増加が喫緊の課題となっているわけですが、そもそも中小企業では賃金アップのための原資に苦慮しているといった声も聞こえており、問題解決は一筋縄ではいかないようです。
【2023年5月号のサマリー】
1. 主時系列でみた首都圏マンション価格・単価・面積の推移!首都圏のマンション価格は過去最高水準に。
2. マンション市場はどのように変化してきたのか?築年数別にみると、マンションの特性は変化してきている。
3. 今後のマンション建て替え需要をどう読んだらよいのか?今後は建て替え需要が増えていくものと予想される。
4. 建設業の倒産件数の推移、工務店の事業継承は進んでいるのか?後継者難から事業を畳むケースも。
5. 企業の生産活動、消費活動は全体としてはポジティブな傾向が継続しているが、個別統計では温度差も。
6. 物価上昇への対応などを理由に中小企業でも賃上げが本格化?従業員のモチベーション向上は大切。
7. アフターコロナ時代において人手不足感が益々深刻化している!人手不足問題は我が国の構造的問題。
8. 株式市場では日米とも下値を切り上げつつあり、日経平均は戻り高値奪回の期待も醸成されている?
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2023/04/26「仕事に活かす経済・不動産レポート」(2023年4月号)
新年度に入って、世の中はアフターコロナの様相を呈してきました。入社式や入学式では、マスク着用を任意とする動きも広がり、街中ではノーマスクの人々も増えてきています。観光地や都内の百貨店では、外国人、日本人問わずコロナ禍前の賑わいが戻ってきました。スポーツ観戦も声出し応援を許容する動きとなり、プロ野球をはじめ各種スポーツ会場は盛況が続いています。
こうしたなか、我が国の構造的問題である「少子化対策」については解決の方向が見えていません。現政権が打ち出している少子化対策にしても、「わかりやすさ」と「使い勝手の良さ」という点でその効果に対して疑問符が持たれています。いっそのこと、①相続税は少子化対策限定に使う、②健康保険の自己負担比率を引き上げる、③国会議員・地方議員の定数を半分にする、といった思い切った政策を示しても良いのではないでしょうか。
少子化対策に取り組んで出生率が改善した自治体では、「議会の定数削減」「住民負担の増加」「子育てしやすい環境」がポイントとなっているようです。
【2023年4月号のサマリー】
1. 主要都道府県における人口流入超過人数と地価動向の関係。人口流入地域では地価も上昇している。
2. 主要都道府県別にみた人口流入超過人数と持ち家、貸家着工動向!人口流入は貸家需要に直結。
3. 東京23区における人口・面積・人口密度、公示地価変動率。東京23区でもバラつきがみられる。
4. 公共工事設計労務単価にみる建設労働者賃金の動きとは。建設労働者賃金は引き続き上昇基調へ。
5. 企業の生産活動、消費活動はまだら模様の展開となっているが、全体としてはポジティブな傾向の印象。
6. あなたは何歳まで働きたいですか?各年代ともに「働けるならいつまでも」という回答割合がトップに。
7. 富裕層は着実に増加しており、今後も保有資産額は増加傾向へ!株価上昇と制度拡充が追い風に?
8. 株式市場では日米ともに戻り高値を試していたものの、景気回復期待とコストアップでボックス相場の様相。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2023/03/22「仕事に活かす経済・不動産レポート(定点観測2023年3月号)をお届けいたします。
不動産市場は経済の新陳代謝の影響によって変化します。
市場を正確に予測するためには、経済状況を定点観測によって把握しておく必要があります。
「経済・不動産レポート(定点観測)」は、各業界から公表されているデータを基に傾向や特徴を分析して解説しております。是非、仕事にお役立てください。
【2023年3月号のサマリー】
1. 小売業全体の販売高及び業態別にみた売上高。店舗展開の変化により不動産仲介要請もさまざま。
2. 百貨店、スーパー、コンビニ業界における現状!スーパー、コンビニ業界ではコロナ禍で消費行動が変容。
3. ドラッグストア、大型家電量販店、ホームセンター業界の現状積!大型店舗の出店・閉店の影響を注視。
4. 最近における外食産業の業態別特徴とは何か?今後のポイントは値上げ動向と魅力的なメニューの開発。
5. 企業の生産活動、消費活動はまだら模様の展開となっているが、全体としては回復傾向を示している印象。
6. アメリカの仕組みに学ぶ賃金上昇のあるべき姿とは何か?賃金上昇は消費拡大、経済成長に繋がるもの。
7. 用途別に見た不動産価格の動き。インフレ進行によって2023年の不動産価格は強い含みで推移する?
8. 株式市場では日米ともに戻り高値を試していたものの、金利上昇と金融リスクの台頭で不安定な展開か?
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。
【レポート作成】一般社団法人 不動産総合戦略協会 客員研究員 水谷 敏也
経歴:日本株建設部門アナリストランキング2007~2017年第一位(11年連続、殿堂入り)
-
2023/02/21「仕事に活かす経済・不動産レポート」(定点観測2023年2月号)
「仕事に活かす経済・不動産レポート(定点観測2023年2月号)をお届けいたします。
不動産市場は経済の新陳代謝の影響によって変化します。
市場を正確に予測するためには、経済状況を定点観測によって把握しておく必要があります。
「経済・不動産レポート(定点観測)」は、各業界から公表されているデータを基に傾向や特徴を分析して解説しております。是非、仕事にお役立てください。
【2023年2月号のサマリー】
1.首都圏及び外環地域における地域経済の動き。住宅着工、小売売上高、有効求人倍率の推移。
2.首都圏及び外環地域における人口流出・流入の動き。茨城県、山梨県、長野県では人口流入超過に。
3.首都圏における新築マンション供給戸数、平均価格、坪単価の推移。価格上昇により床面積は縮小へ。
4.IMFによる世界経済見通しでは2023年を若干の上方修正!中国とインドが牽引役となる見通し。
5.企業の生産活動、消費活動は一部で減速感が台頭しているものの、一定水準は維持している印象。
6.値上げしても売れるもの、値上げしたら売れなくなるものとは何か?ブランド品の売れ行きは落ちない。
7.2022年の倒産件数・負債総額は増加に転じたが、今後の見通しは?人手不足解消がキーワード。
8.株式市場では日米ともに戻り高値を試している展開となっているが、景気悪化懸念から上値は重い印象。 -
2023/01/24「仕事に活かす経済・不動産レポート」(2023年1月号)
物価高が一段と浸透しています。2022年12月の消費者物価指数は41年振りの高い伸び率となっており、こうした動きは2023年も続きそうです。企業は原価高に苦しんでおり、これまで堅調に推移していた食品や外食企業も減益或いは減額修正を余儀なくされています。
外食大手のマクドナルドも値上げを打ち出しており、こうした値上げの動きは一段と広がりそうです。大企業では賃上げの動きが出ていますが、経営体力の弱い中小企業にまで賃上げの動きが広がるか否か予断を許しません。
一方、日銀も低金利政策からの転換を余儀なくされつつあり、インフレ退治と景気回復という難しい舵取りを迫られています。2023年は楽観視できない厳しい年となりそうです。
【2023年1月号のサマリー】
1.2023年の物価は上昇基調が続くのか、下落に転じるのか?2023年はインフレとの闘い元年となる。
2.人手不足問題は益々深刻化、いよいよ人生100年勤労時代へ!人手不足は全国に広がっている。
3.首都圏における沿線別鉄道会社の業績と利用客数の推移と展望!テレワーク文化の浸透がブレーキに。
4.主な小売業、外食企業の売上高及び営業利益の推移と展望!物価高が収益を圧迫する状況が続く。
5.日銀の政策転換に伴う建設・不動産市場への影響をどう読むか?インフレ傾向は続くとの前提が賢明。
6.土地活用の仕方(空き家問題、空き店舗問題)を考える?建物の維持・管理がポイントとなる。
7.企業の生産活動、消費活動は一部で減速感が台頭しているものの、一定水準は維持している印象。
8.街が変わるとお金の使い方はどう変わっていくのか?居住者の特徴によってお金の使い方が変化してくる。
9.外国人観光客はどこまで戻るのか、期待と不安が交錯!交通・観光業の人手不足がボトルネックに。
10.株式市場では日米ともに戻り高値を試す展開となっているが、景気悪化懸念から上値が重くなっている。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2022/12/21物価高が景気に影を落としつつあります。10月の全国消費者物価指数は前年比3.6%上昇し、40年8カ月振りの高い伸び率となりました。相次ぐ値上げを受けて、回復が見込まれていた景気マインドも低下しつつあります。
足元では物価の優等生と言われる「卵」が、11月には前年比27%も値上がりしました(JA全農たまごMサイズ1キロ)。この要因については、ニワトリの餌となるトウモロコシなどの飼料価格が高騰しているためとみられています。
また、正月のおせち料理にも値上げの影響が出ており、仕出し料理店によると例年よりおよそ3割程度の値上げとなる模様です。さらに、年明けもさまざまな分野で値上げが予定されており、まさに2023年は物価高との闘いの火ぶたが切って落とされようとしています。
【2022年12月号のサマリー】
1.建設・住宅・不動産の2022/9上期決算を総括する。ゼネコンは不調、住宅・不動産は堅調と明暗。
2.業態別にみてリアル店舗の出店予測はどうなるのか?テイクアウト、専門店の浸透が統廃合を加速か。
3.企業の生産活動、消費活動は順調に推移しているものの、業態別による温度差が拡大している印象。
4.富裕層の定義、行動パターン、消費マインドを考える。最大の関心事は自身の健康と子孫への資産継承。
5.2023年も食品分野を中心に値上げラッシュが続く見通し!春先には公共交通機関の値上げも視野に。
6.株式市場では日米ともに戻り高値を試す展開となっているが、景気悪化懸念から上値が重くなっている。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2022/11/28我が国において物価上昇の波が強まりつつあります。すでに、企業間取引の価格動向を示す企業物価指数は前年比で9%前後の高い伸び率となっていますが、消費者物価指数も30年振りの高い伸び率を示しています。
先日発表された10月の東京都消費物価指数は40年振りの伸び率となりました。何れ、東京都の状況が全国に波及していくものとみられています。また、足元では人手不足と物価高によって企業倒産件数が増加に転じています。
人手不足と物価高を放置すれば、事業そのものが立ちいかなくなってくるケースも増えてくるかもしれません。コロナ禍後はインバウンド需要や国内観光需要回復が期待されていますが、人手不足によって現場が回らないといった事態を想定しておく必要があると思います。
【2022年11月号のサマリー】
1.首都圏不動産市場を取り巻く2023年の予想天気図とは?天気は回復傾向だが、快晴には程遠い。
2.2023年の経済、株価、為替、金利をどうみるか?株価下落、ドル高、金利上昇の局面からの転換も。
3.企業の生産活動、消費活動は順調に推移しているおり、小売売上高はコロナ禍前を上回る動きも。
4.内部告発の潮流が社会を浄化するのは本当か?内部告発とは自己を犠牲に社会のために行動すること。
5.パート、アルバイト、派遣社員の募集時時給動向について!コロナ禍で職種別に時給格差が出ている。
6.株式市場では日米ともにインフレ率低下、景気動向を睨みながら戻り高値を試す展開となっている。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。 -
2022/10/25円ドル相場は10月20日に32年振りに150円台を付けるなど一段の円安が進んでいます。円安は輸出企業にとってプラスに作用しますが、インバウンド再開によって外国人観光客による国内消費の押し上げが期待されています。
10月11日の入国制限撤廃によって、外国人観光客が大きく増えていますが、円安進行によって我が国の消費財に対する割安感が一段と台頭し、小売店舗や観光地での「爆買い」が期待されています。為替水準の見方についてはいろいろな議論がありますが、少なくとも消費喚起は景気回復の呼び水になるといえそうです。
一方、我が国の9月の企業物価指数(企業間取引おける物価指数)は市場予想を大きく上回り、前年同月比9.7%増と19カ月連続上昇しました。また、9月の消費者物価指数(生鮮食料品を除く総合指数)は31年振りに3%台の上昇を示しました。いよいよ本格的な物価上昇局面へと入りつつある印象です。
【2022年10月号のサマリー】
1.アフターコロナの最大の課題は人手不足問題か?人手不足問題はコロナ禍後の経済回復にとって足かせ。
2.円安の影響も加わり、倒産件数が増えつつある。2022年度上期の倒産件数は3年振りに増加。
3.企業の生産活動、消費活動は順調に推移しているが、建設受注、持ち家着工などまだら模様の展開も?
4.ハラスメントの横行が社会を不安定にする?ハラスメントを放置している企業は社会から淘汰される。
5.地価の回復傾向は本物なのか?経済活動の正常化が進むなかで、全国的に地価の回復傾向が進む。
6.株式市場では日米ともにインフレ、景気減速リスクを織り込んで下値模索型の展開となっている。
※当レポートは、各方面で公表されたデータの分析とインタビューを基に構成しています。